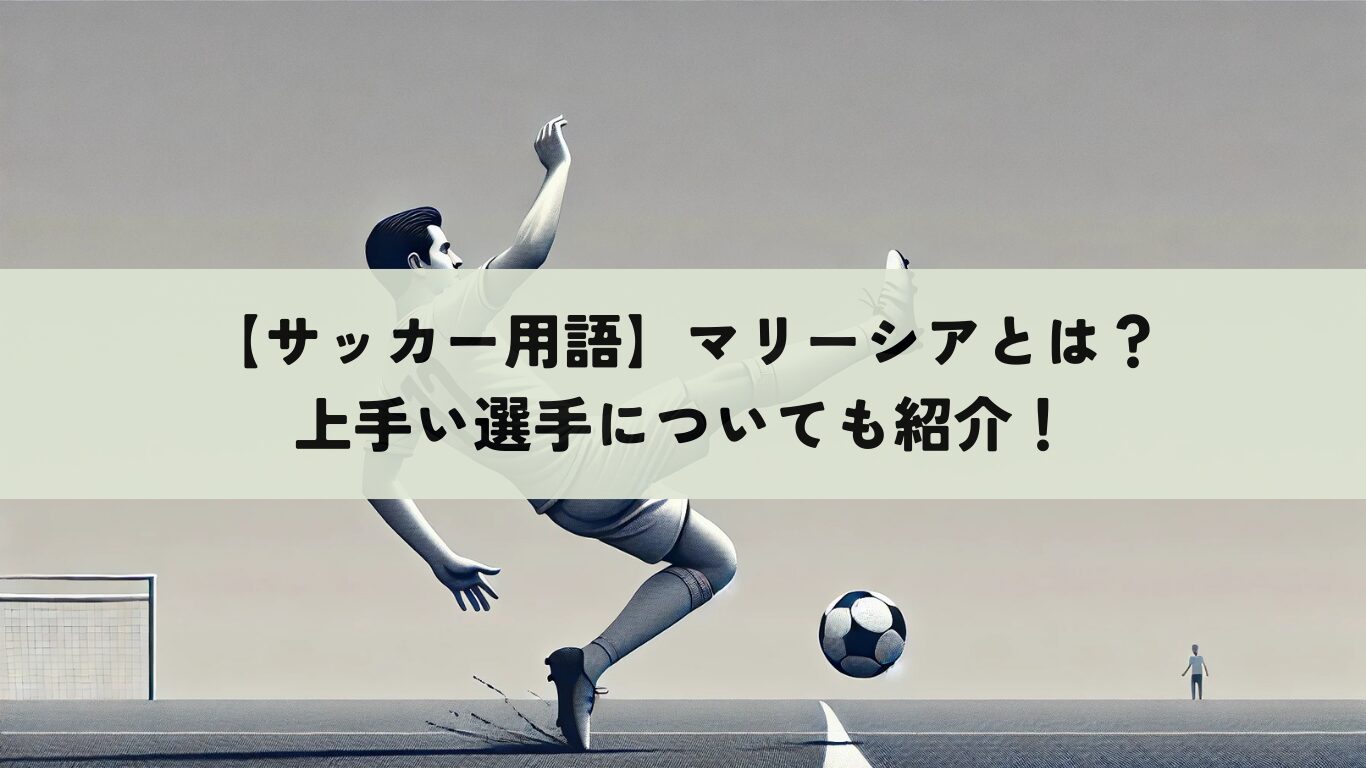サッカーの試合を観戦していると、時折耳にする「マリーシア」という言葉。これは、単なる技術や戦術とは異なる、選手の知恵や駆け引きを指す特別な用語です。
今回は、サッカー初心者の方にも分かりやすく、この「マリーシア」の意味や、それを巧みに使いこなす選手たちのエピソードを紹介します。
マリーシアとは?

マリーシアの意味
「マリーシア(Malicia)」は、ポルトガル語で「ずる賢さ」や「機転の利いた駆け引き」を意味する言葉です。サッカーにおいては、ルールの範囲内で巧みに立ち回り、試合を有利に進めるための知恵や駆け引きを指します。
例えば、
- 相手のファウルを誘うプレー
- 時間稼ぎのテクニック
- 心理戦を駆使して相手のペースを乱す
といったプレーが挙げられます。
マリーシアとシミュレーションの違い
「マリーシア」と「シミュレーション」は似ていますが、根本的に異なります。
- シミュレーション → 故意に倒れてファウルをもらおうとする「反則行為」
- マリーシア → ルールの範囲内で行う「賢い駆け引き」
つまり、マリーシアはフェアプレーの精神を持ちつつ、試合を有利に進めるための戦術的スキルとも言えます。
マリーシアの具体例

ファウルを誘うプレー
例えば、相手ディフェンダーが足を出してきた瞬間に巧みに接触し、ファウルをもらうプレーがあります。これは、相手の動きを読み、機転を利かせたテクニックの一つです。
時間稼ぎ
試合終盤でリードしている際に、
- コーナーフラッグ付近でボールをキープ
- スローインをゆっくり行う
といったプレーで時間を使うのも、マリーシアの一例です。
相手の心理を突く
試合中に相手選手に言葉を投げかけ、焦らせたり怒らせたりすることで、相手の冷静さを失わせるのもマリーシアの一種とされています。
マリーシアを体現した上手い選手たち
ディエゴ・マラドーナ
アルゼンチンのレジェンド、ディエゴ・マラドーナは、1986年ワールドカップでの「神の手」ゴールで有名です。審判に気づかれないように手でゴールを決めるというプレーは、マリーシアを象徴する一例と言えるでしょう。
ネイマール
ブラジル代表のエース、ネイマールは、巧みなドリブルとファウルをもらうスキルを兼ね備えています。相手の守備の動きを読みながら、巧妙に接触を誘発するプレーが特徴的です。
セルヒオ・ラモス
スペイン代表の元キャプテン、セルヒオ・ラモスは、相手のメンタルを揺さぶる心理戦が得意なディフェンダーです。重要な試合では巧みに相手を挑発し、ペースを乱すことで試合を有利に進める場面が多く見られました。
マリーシアの文化的背景

ブラジルにおけるマリーシア
ブラジルでは、マリーシアはサッカーだけでなく、日常生活における「機転」や「柔軟な対応力」を指します。困難な状況を切り抜ける知恵や、状況を見極めて有利に立ち回る能力が評価される文化です。
日本におけるマリーシアの捉え方
日本では、マリーシア=ずる賢さとネガティブに捉えられることが多いですが、近年は試合巧者になるための賢さとして再評価されています。
元ブラジル代表のドゥンガが「日本人選手にはマリーシアが足りない」と指摘したこともあり、日本サッカー界でも注目されつつあります。
マリーシアの現代的な意義
VARの導入とマリーシア
VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)の導入により、
- 過度なファウルの誘発
- シミュレーションによる誤審
といったマリーシア的プレーが減少しつつあります。しかし、選手たちはルールの中で新たな駆け引きを模索し続けており、マリーシアの概念は変化しながら生き続けています。
フェアプレーとの共存
マリーシアは、決してスポーツマンシップに反するものではなく、試合を戦略的に進めるための知恵として活用することが重要です。
例えば、
- 相手のミスを誘う巧みなプレッシング
- 試合の流れを読むポジショニング
なども、マリーシアの一種と言えるでしょう。
まとめ:マリーシアの価値とは?
マリーシアは、
- 試合を有利に進めるための知恵
- 相手との駆け引きを制するスキル
- 心理戦を活用したプレー
といった要素を含んでおり、サッカーの戦術として欠かせない要素です。
「賢さ」と「ずる賢さ」の境界線は時に曖昧ですが、サッカーにおいては、ルールの範囲内で相手を上回ることこそが勝利への近道。現代サッカーでも、マリーシアの概念は形を変えながら生き続けています。
これからサッカーを観戦する際は、「どの選手がマリーシアを使っているか?」に注目すると、新たな楽しみ方が見つかるかもしれません。