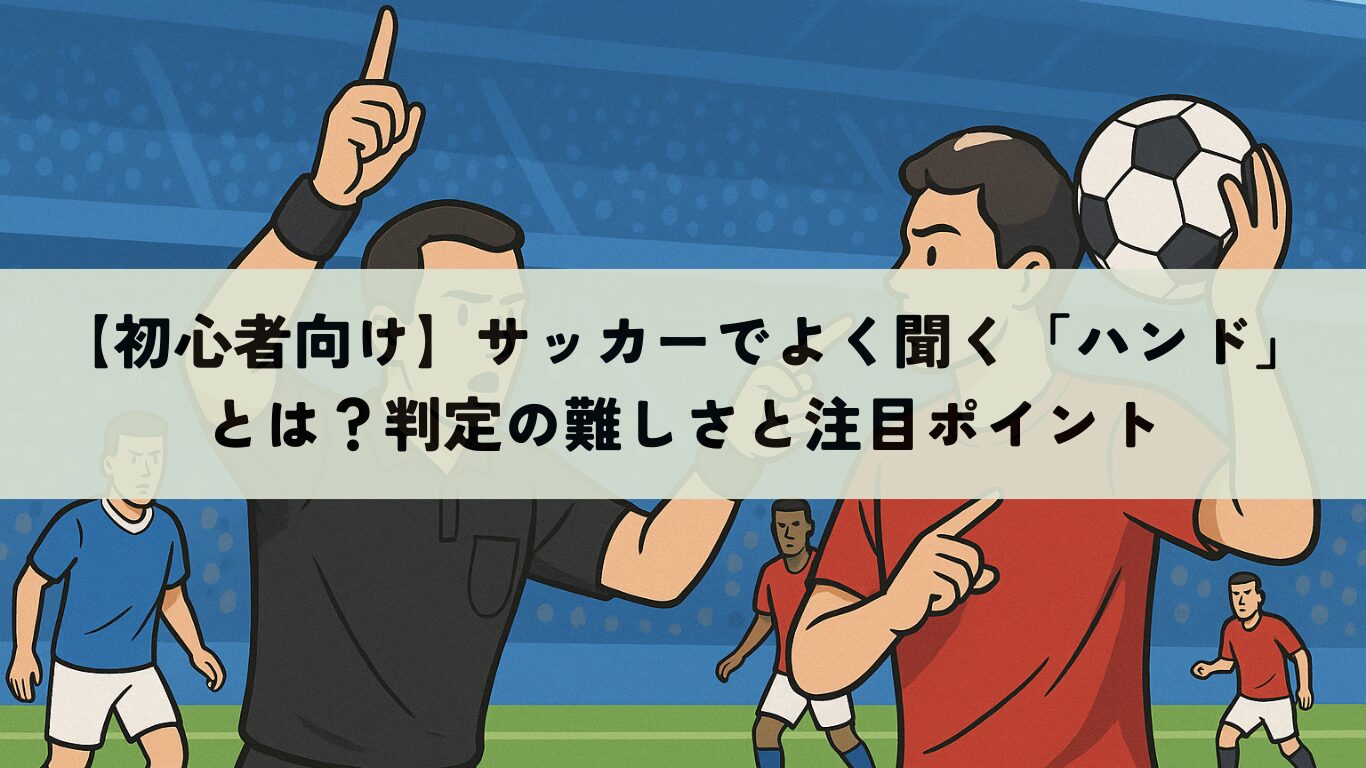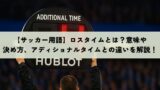サッカーを観ていると「ハンドを取られた!」「いや、あれはハンドじゃない!」と議論が巻き起こるシーン、よく見かけますよね。
でも、サッカー初心者にとっては「そもそもハンドってどんなルール?」「手に当たったら全部反則なの?」と、疑問がわいてくるもの。
この記事では、サッカーにおける「ハンド」の基本ルールや、判定が難しい理由、注目ポイント、さらには世界中で話題になったハンドのエピソードまで、フランクにわかりやすく解説していきます!
ハンドとは何か?基本ルールをおさらい

ハンド(Handball)とは、意図的に手や腕を使ってボールに触れる反則のことです。
ここでいう「手や腕」とは、肩より下の部分が対象です。
ざっくり覚えよう
- 肩より下にボールが意図的に当たる → ハンドファウル
- 自然な体勢で偶然ボールが当たる → 原則、ハンドではない
重要ポイント
- 「意図的かどうか」が判断基準
- 手や腕の位置が「不自然」であれば、意図がなくてもハンドになる場合がある
つまり、「わざとじゃなくても反則になるケースがある」んです!これがハンド判定を難しくしている理由でもあります。
なぜハンドの判定は難しいのか?

「意図的か偶然か」の判断が超難しい
選手の動きは高速なので、審判が瞬時に意図を読み取るのは至難の業。
「体を大きく見せる動き」が微妙なライン
- シュートブロックで腕が広がる
- クロスを防ぐときに自然に手が上がる
こういった動きは「不自然」と見なされ、ハンドを取られることがあります。
VAR導入後、さらに基準がシビアに
ビデオ判定(VAR)が導入されてからは、ミリ単位の判定が可能になり、
- 肩?腕?どっち?
- 手にわずかに触れたか?
など、超細かいジャッジが試合を左右する場面も増えました。
有名なハンド事件・エピソード集
■ 「神の手ゴール」(マラドーナ/1986年W杯)
伝説的なハンド事件といえばこれ!
メキシコW杯準々決勝・アルゼンチンvsイングランド戦。
ディエゴ・マラドーナがジャンプしてパンチ気味にボールをゴールへ押し込んだにもかかわらず、審判が見逃してゴールが認められた!
「少しマラドーナの頭と、少し神の手が触れた」
と本人も後に語ったほど(笑)。
■ フランス vs アイルランド(2010W杯予選)
ティエリ・アンリが手でボールをコントロールしてアシスト、ゴールが生まれてしまった事例。
試合後、世界中から「VARがあれば…」と嘆きの声が上がり、VAR導入のきっかけの一つにもなった事件です。
■ リバプール vs トッテナム(プレミアリーグ2019)
守備側の選手の手にボールが微妙に当たっただけでPKを取られ、大騒ぎに。
「そんなの防げるわけない!」というファンと、「ルール通り!」というジャッジ擁護派に分かれ、世界的な議論を巻き起こしました。
現行ルールのハンド基準(2025年版)

FIFA公式によると、ハンドの反則は以下のように定義されています:
ハンドと見なされるケース
- 腕や手を使ってボールの動きを明らかにコントロールした場合
- 意図的に腕を広げて体を大きく見せる動きをした場合
- 腕が不自然な位置にあり、ボールが当たった場合
ハンドと見なされないケース
- 近距離から避けられない形でボールが当たった場合
- 自分の身体(足、頭)から跳ね返ったボールが手に当たった場合
つまり
- 「意図」だけじゃなく、「手の位置」も重視される
- 「逃れようがない当たり方」は免責される
このあたりがポイントです!
ハンド判定で注目すべきポイント3つ
手や腕の位置
ボールに当たった時の手の位置が自然か、不自然か。
選手の意図
明らかにボールに向かって手を動かしていたら、ハンド確定です。
ボールまでの距離とスピード
至近距離かどうかも重要な判断要素です。
近距離で体に跳ね返った場合は、たとえ腕に当たってもハンドにならないケースが多いです!
まとめ|ハンドを理解してサッカーをもっと深く楽しもう!
- ハンドとは「意図的に手や腕でボールに触れる反則」
- ただし、近年は「意図」だけでなく「腕の位置」や「回避可能性」も考慮される
- 有名なハンド事件がVAR導入にも影響を与えた
- 試合中のハンド判定は意外と主観的で、議論を呼びやすい
これからサッカーを観る時、ハンド判定が入ったら、
- 「今のは意図的だった?」
- 「腕の位置、不自然だった?」
とちょっとだけ考えてみると、試合の見方が何倍も深くなりますよ!
サッカー観戦をもっと楽しくするために、ぜひ「ハンドマスター」を目指しましょう!