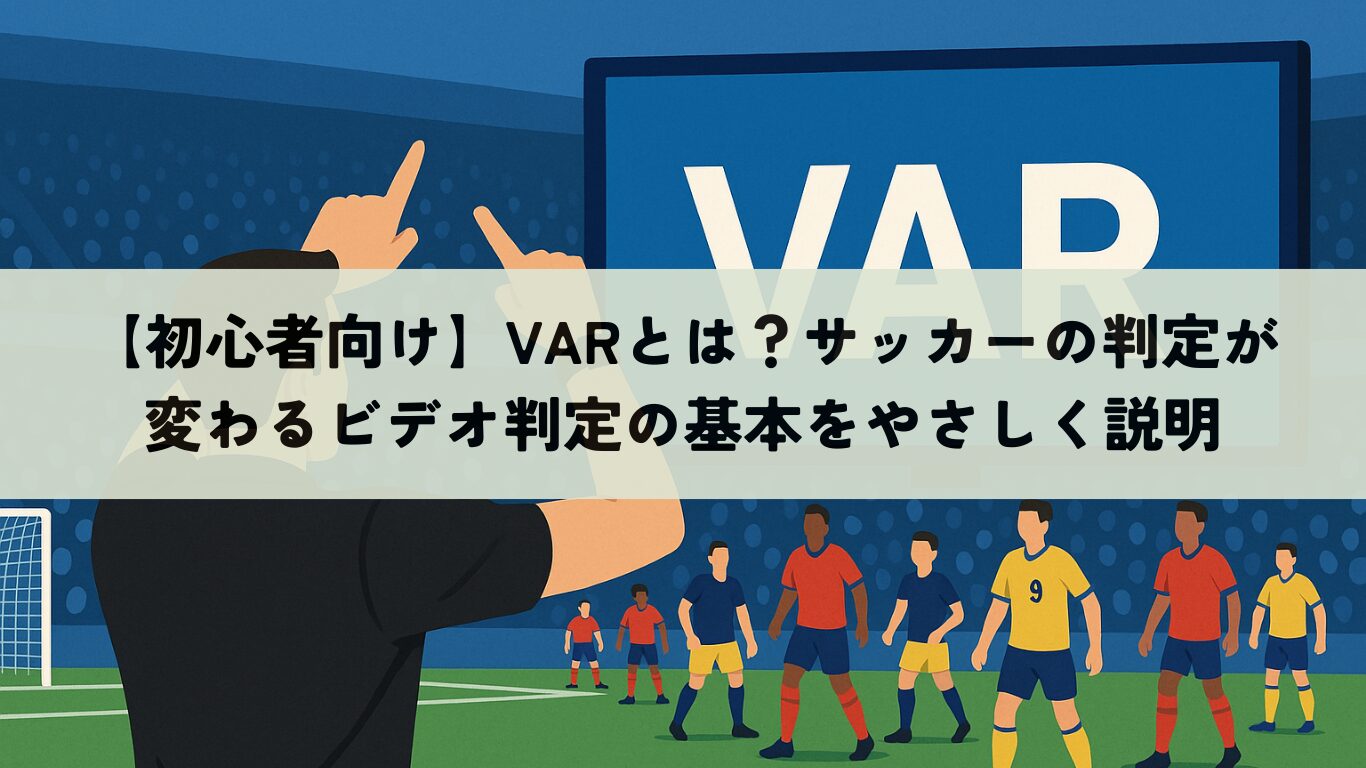「VARでゴールが取り消されました!」
サッカー中継を観ていると、最近よく聞くこの言葉。「え?何が起きたの?」「なんで点が取り消されたの?」とモヤモヤしたこと、ありませんか?
この「VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)」は、近年サッカーのルールと試合展開を大きく変えた革命的な技術なんです。
この記事では、サッカーを見始めたばかりの方でもわかるように、VARの仕組み、使われる場面、実際に試合で起こったドラマチックなエピソードまで、やさしく楽しく解説していきます!
VARとは何か?

VAR(Video Assistant Referee)とは、ビデオ映像を使って審判の判定をサポートする仕組みのこと。
主審だけで判断が難しい場面で、スタジアム内に設置された複数のカメラ映像を確認しながら、専属のVAR担当審判が「これは見直した方がいいかも」と助言します。
簡単に言うと
- ビデオ判定の専門チームが控室でモニターを見ている
- 主審に「ちょっと待った!チェックしてみて」と連絡
- 主審がピッチ脇のモニターでリプレイを確認
- 必要なら判定を変更!
VARはあくまで「主審の補助」。最終判断はあくまで主審が下します。
VARが使われるのは4つのケースだけ!
FIFAの公式ルールによれば、VARが使えるのは以下の4つの場面だけです:
- ゴールに関する判定(オフサイドやファウルなど)
- PK(ペナルティキック)の判定
- 一発レッドカード(退場)の場面
- カードの対象選手の誤認(違う選手にカードを出したなど)
「些細なファウル」や「スローインの方向」など、全てのプレーに使えるわけではありません。
ドラマを生んだVARの実例エピソード

W杯2018:フランス vs オーストラリア
この試合はVARがワールドカップで初めて得点に直結した瞬間として有名です。
前半にグリーズマンが倒され、当初は流されたプレーがVARにより見直され、PK判定に変更。
→ フランスが先制点を決め、最終的にこの試合に勝利。そのまま優勝まで駆け上がった…!
プレミアリーグ:スターリングの“つま先”オフサイド
マンチェスター・シティのラヒーム・スターリングが決めたゴール。
VARによって、つま先が数センチ出ていたとしてオフサイドと判定されノーゴールに。
→ ファンからは「そこまで厳密にやる必要ある?」と議論が巻き起こる。
このように、ミリ単位の判定が可能になったことで試合の流れが大きく変わることも。
日本代表にもVARの恩恵が
2022年W杯グループステージ、スペイン戦での三笘薫の“ラインギリギリ折り返し”が話題に。
VARで検証した結果、「ボールの一部がライン上に残っていた」としてゴールが認められ、日本が逆転&決勝トーナメント進出を決める歴史的瞬間に!
VARのメリットとデメリット
メリット
- 誤審の防止:大舞台での“致命的ミス”を減らせる
- 正確性の向上:映像で確認できるので納得感がある
- フェアな試合進行:選手やファンの信頼感が高まる
デメリット
- 試合の流れが止まる:テンポが悪くなることも
- 判断基準の曖昧さ:同じようなプレーでもVAR介入する/しないの差が出る
- 過度な機械的判定:人間味のある“流し”がなくなるという声も
世界中でのVAR導入の流れ

VARはまずテスト運用(2016年)→正式導入(2018年W杯)→現在は主要リーグで常設という流れで広がっています。
導入済みの代表的なリーグ・大会
- FIFAワールドカップ(2018年〜)
- UEFAチャンピオンズリーグ
- プレミアリーグ
- ラ・リーガ
- セリエA
- ブンデスリーガ
- Jリーグ(2020年〜)
つまり今や“VARなしのトップサッカー”はほぼ存在しない時代に突入しているわけです!
まとめ|VARを知れば、サッカー観戦がもっと面白くなる!
- VARとは、ビデオ映像で主審の判定をサポートする制度
- 使えるのは「得点」「PK」「レッドカード」「選手の誤認」の4場面のみ
- 正確な判定が増える一方、テンポの悪さや納得感に課題も
- ミリ単位のドラマが展開される現代サッカーでは、VARが試合の流れを左右するカギに!
これからサッカーを観るとき、「VARが入った!なぜだろう?」と考えてみると、より深く試合を楽しめるはずです。
ルールを知るとサッカーはもっと面白い!次の試合では、“VARのある世界”ならではの展開にもぜひ注目してみてくださいね!