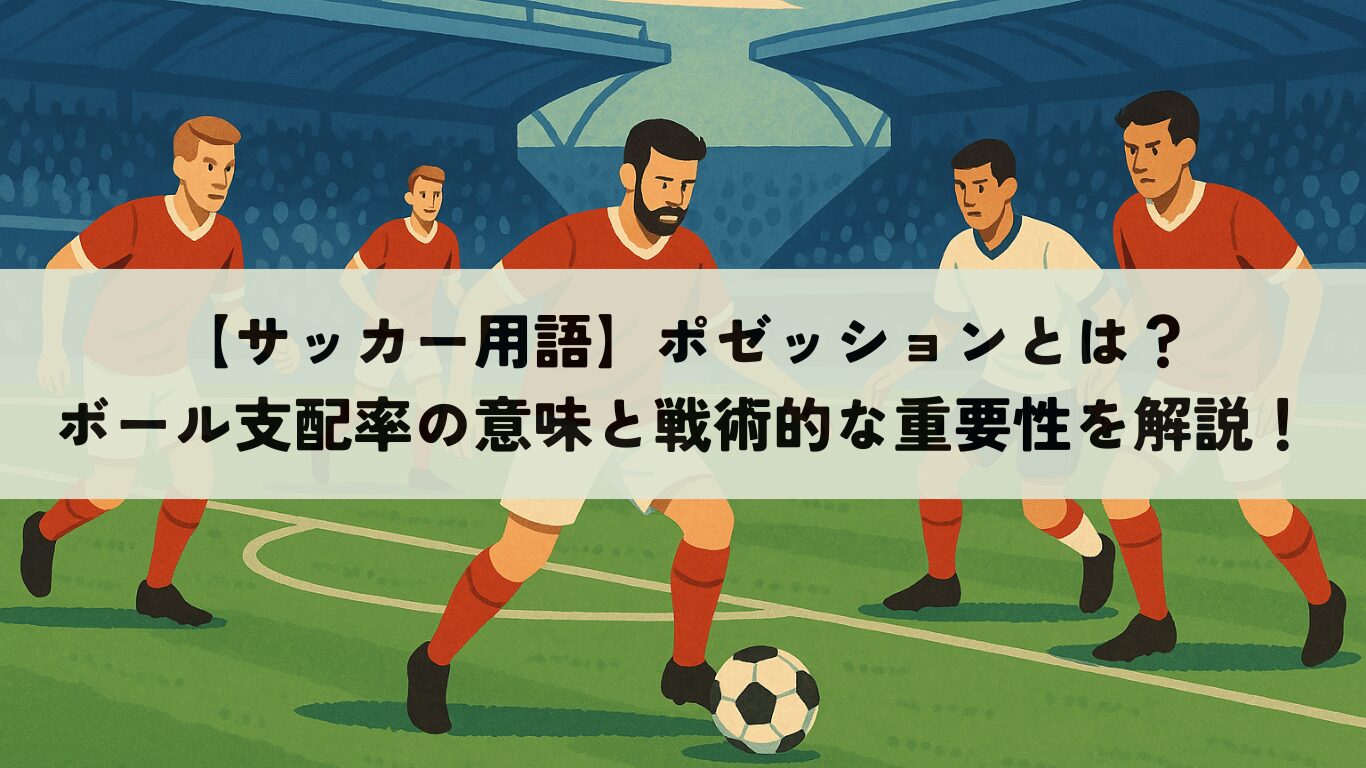サッカー中継で「ポゼッション率は70%です」と言われても、「それってすごいの?勝ってるってこと?」と疑問に思ったこと、ありませんか?
この記事では、サッカー初心者にもわかりやすく、「ポゼッション」とは何か、その意味と使い方、そして戦術としての役割まで徹底解説していきます。さらに、世界のトップクラブや選手の実例とエピソードを交えて、読んで楽しい&試合がもっと面白くなる内容にしています!
ポゼッションとは?

「ポゼッション(Possession)」とは、ボール支配率のこと。
つまり、「試合中、どれだけの時間ボールを保持していたか」を数値で示したものです。
たとえば
- Aチーム:ポゼッション率68%
- Bチーム:ポゼッション率32%
→ この場合、Aチームが試合の約7割の時間、ボールを持っていたという意味になります。
ポゼッションが高い=試合を“支配している”とも言われますが、実は必ずしも勝利と直結するわけではない点もポイントです(後述)。
なぜポゼッションが重要視されるのか?
相手に攻撃のチャンスを与えない
ボールを持っている時間が長ければ、それだけ相手にチャンスを与えるリスクが減る。
自分たちのリズムで試合を進められる
高いポゼッション率は、テンポの主導権を握ることにもつながります。相手を動かし、疲れさせ、隙をつく。
相手の守備陣形を崩す
左右にボールを回し続けることで、相手守備を引きずり出してスペースを作る戦術に繋がる。
ポゼッション=勝利ではない?

よくある誤解が、「ポゼッション率が高い=勝つ」というイメージ。
でも実際には、ボールを持っているだけではゴールは生まれません。
有名な例:レスター vs マンチェスター・シティ(2016)
レスターが優勝した2015-16シーズンの対マンチェスター・シティ戦、ポゼッション率は30%台にも関わらず、3-1で快勝。
→ カウンター(速攻)主体のチームは、ボールを持たずに勝つ戦術を得意とします。
つまり、ポゼッションは手段であって目的ではないというわけです!
ポゼッションスタイルの代表チーム・監督・選手
FCバルセロナ(2008〜2012)
ジョゼップ・グアルディオラ監督時代のバルサは、「ティキ・タカ」と呼ばれる超ハイポゼッションスタイルで欧州を席巻。
キープレイヤー:シャビ、イニエスタ、ブスケツ
- ボールを細かく動かして、90分間試合のテンポを支配。
- 実際に80%を超える試合も多数。
ある試合では、敵の監督が「ボールを1回も触れなかったような気がする」とコメントしたほど。
マンチェスター・シティ(ペップ・グアルディオラ監督)
現在のシティも、ポゼッションをベースにしたハイブリッド戦術を採用。
キープレイヤー:ロドリ、ベルナルド・シウバ、エデルソン
- 守備陣からのビルドアップ(後方からの組み立て)も非常に巧み。
- ゴールキーパーのエデルソンが長短のパスで試合をコントロールするのも特徴。
ポゼッション率が低くなった試合(例:CLの決勝戦)では逆に崩れる場面も。つまり、彼らの生命線はボール支配にあるとも言えます。
スペイン代表(EURO 2008〜2012)
バルセロナの中心選手を多数起用したスペイン代表も、国際大会で「ポゼッション無双」を見せつけました。
- EURO2008、2012、W杯2010で優勝
- 毎試合70%超の支配率
2014年W杯では「ポゼッションだけでは勝てない」ことも露呈。オランダに1-5で大敗し、ボールを持っていても決定力がなければ意味がないことが話題に。
ポゼッションを高めるために必要な要素

技術のある選手
ボールを失わないためには、正確なパスとトラップが必要。
ポジショニングとオフザボールの動き
味方がボールを持ったとき、どこに動くか?が“次のパスコース”を作る鍵。
チーム全体の共通意識
「どこでボールを回すか」「どのタイミングで縦に入れるか」など、連動性が重要です。
ポゼッションに頼らない“新しい支配”もある
近年では、「ポゼッションは重視しないが支配している」スタイルも増えています。
例:クロップ式ゲーゲンプレス(リヴァプール)
- ボールを持たれた後の即時奪回(トランジション)に重点
- ポゼッション率はそこまで高くなくても、“主導権”を握っている感覚
→「支配=ボール保持」だけじゃない、という進化系です。
まとめ|ポゼッションの理解で試合がもっと面白くなる!
- ポゼッションとは、ボール支配率のこと
- 高ければ試合の主導権を握れるが、それだけでは勝てない
- バルサやシティ、スペイン代表はポゼッションで世界を制した
- でもカウンターやプレス重視のチームも勝てる
要するに、サッカーは「支配vs効率」の戦いでもあります。
次の試合では、単に「点が入った/入らない」だけでなく、 「今どっちがボール持ってる?」「なぜポゼッションを狙ってる?」 という視点でも観てみてください。
きっとサッカーがもっと深く、もっと面白くなりますよ!