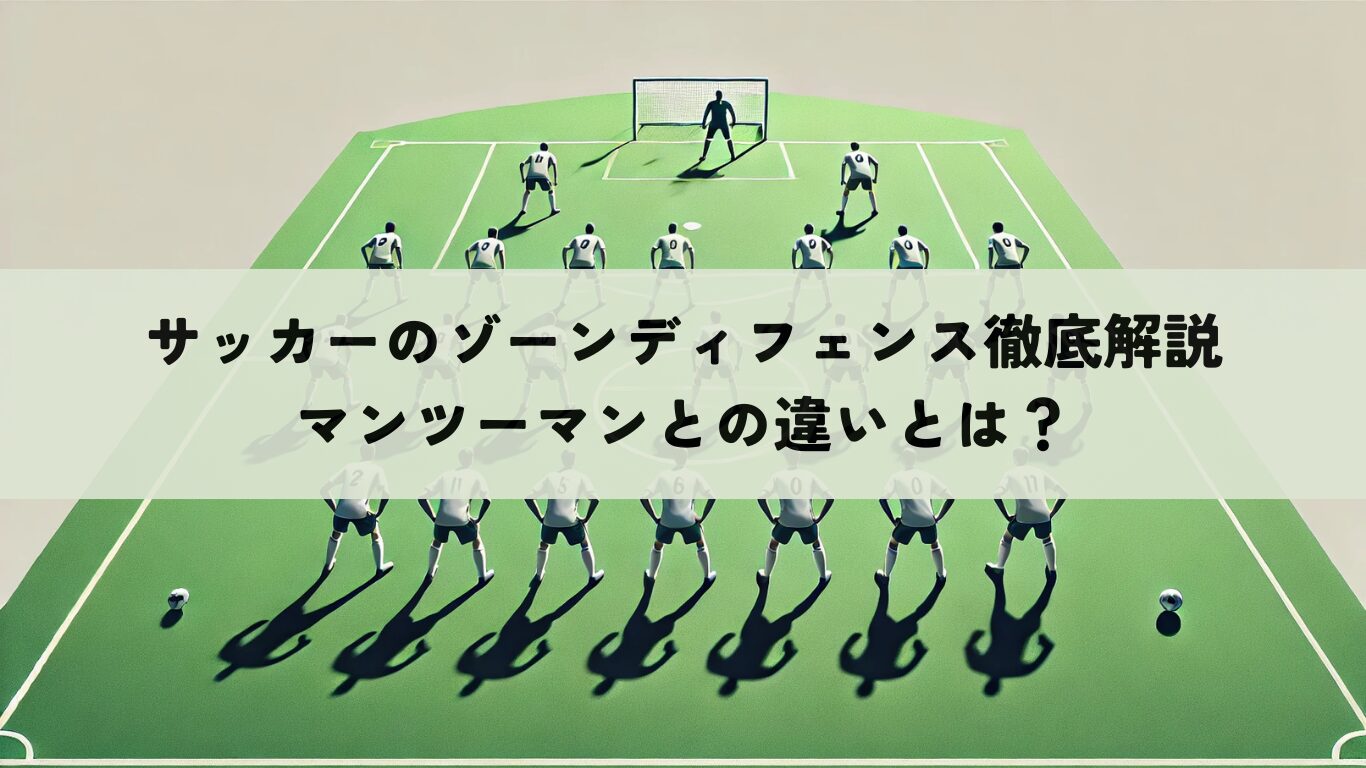サッカーに興味を持ち始めたとき、よく耳にするのが「ゾーンディフェンス」や「マンツーマンディフェンス」といった守備の用語。なんとなく聞いたことはあるけど、「結局どう違うの?」「どっちが強いの?」って思ったことありませんか?
この記事では、ゾーンディフェンスの仕組みと特徴を中心に、マンツーマンとの違いや、実際にゾーンディフェンスを極めた選手やチームのエピソードを交えて、サッカー初心者にもわかりやすく解説していきます!
ゾーンディフェンスとは?

ゾーンディフェンスは、選手が特定の「エリア(ゾーン)」を守る守備のスタイルです。
- 相手選手ではなく、自分のゾーンに入ってきた相手に対応する。
- ポジショニングと連携が命。
- チーム全体でスライド(横移動)してバランスを保つ。
つまり、ボールの動きに応じて全員がポジションを微調整しながら、チーム全体で守備ブロックを形成するのがゾーンディフェンスです。
メリット
- 組織的な守備ができる
- 1人が抜かれてもすぐカバーできる
- 疲労の分散ができる(特定の選手に負担が集中しにくい)
デメリット
- 個人の判断が遅いと崩されやすい
- 連携ミスが命取りになる
マンツーマンとの違いは?

マンツーマンディフェンスは、特定の相手選手を1人のディフェンダーがずっとマークし続ける守備。
- 相手の動きに100%ついていく。
- 個人の守備能力が重要。
- 連動よりも1対1の勝負が中心。
わかりやすく例えると…
- ゾーンディフェンス=「陣地を守る陣形」
- マンツーマン=「鬼ごっこで相手をマークし続ける」
現代サッカーでは、この2つをハイブリッドで使うチームがほとんどです。
ゾーンディフェンスを極めたチーム&監督たち
アリゴ・サッキ(元ACミラン監督)
ゾーンディフェンスの代名詞とも言える人物が、80年代後半のACミランを率いたアリゴ・サッキ。それまで主流だったマンマークに革命を起こし、全員が連動して動くゾーンディフェンスを構築。
有名なエピソード: サッキは練習中、相手がいなくても「見えない敵」を想定してディフェンスラインの連動を徹底的に叩き込んでいたそう。彼の理論は、のちにペップ・グアルディオラやユルゲン・クロップらにも影響を与えました。
ディエゴ・シメオネ(アトレティコ・マドリード)
シメオネ率いるアトレティコは、現代でもっとも「守備的ゾーンディフェンス」が機能しているチームのひとつ。
4-4-2のブロックをコンパクトに保ち、中央を完全に封鎖。相手にボールを持たせるが、決定機は与えないという戦い方。
印象的な試合: 2016年のCL準決勝 バイエルン戦。ボール支配率は20%台でも、守備とカウンターだけで決勝に進出した試合は、守備戦術の教科書とも言われています。
ゾーンディフェンスの中のロール(役割)を見てみよう

センターバック(CB)
- 最終ラインのコントロールタワー。
- 味方のラインを整えながら、声での指示も重要。
- ゾーンでの「間」に入ってくる選手の処理が鍵。
サイドバック(SB)
- サイドのゾーン管理と、時に1対1の対応。
- オーバーラップのタイミングもゾーンのバランスを見て判断。
ボランチ(DMF)
- 守備時はゾーンの穴埋め役。
- 特に相手のトップ下の侵入を防ぐのがポイント。
現役選手で見る「ゾーンディフェンスの鬼」
ヴィルヒル・ファン・ダイク(リヴァプール)
「守備範囲が広すぎる男」。
ファン・ダイクは、ゾーンディフェンスの中でも一人で複数のエリアをカバーできる選手。守備の読みとポジショニングが秀逸で、あえて“飛び込まない”守備で相手を迷わせます。
2020年のプレミアリーグで、1対1で抜かれた回数が“0”という驚異の記録を達成。
カゼミーロ(マンチェスター・ユナイテッド)
中盤のゾーン守備の達人。
ボールを奪う能力だけでなく、スペースの埋め方が絶妙。相手のパスコースを自然と消すような立ち位置が特長。
レアル・マドリード時代、モドリッチ&クロースの攻撃的な役割を可能にしたのは、カゼミーロのゾーン守備あってこそと言われています。
まとめ
ゾーンディフェンスは、サッカーにおける「組織的守備」の核心です。
- エリア(ゾーン)を守る意識が大事
- 個人技より「連携」「ポジショニング」がカギ
- マンツーマンと組み合わせて使うのが現代流
そして、ゾーンディフェンスが極まったときの守備は、まさに芸術。名将や名選手たちのエピソードから学ぶことで、試合の見え方も変わってくるはず!
サッカーをもっと深く楽しむ第一歩として、ぜひゾーンディフェンスの奥深さを味わってみてくださいね!